おもちゃの種類って本当にたくさんありますよね。
その中から、子供が本当に楽しめるおもちゃが見つかれば最高です。
でも、親としては「好奇心や興味を育んでくれたら」とか「理科を好きになってほしい」といった
”プラスアルファ”を期待してしまいがちです。
そんな親子にとって、『実験系のおもちゃ』は期待に応えてくれると思います。
うちの子供たちが遊んでいるのは、”走る!Necoライト”です。
ハンドルを回すと、おもちゃが走ったり光ったり音を出したりします。
子供達は「自分の力で変化が起こる」体験にとても興味があるようです。
この記事では、手回し発電機のおもちゃが子どもの成長にどのような良い影響を与えるのか、また選び方や遊び方のポイントをまとめます。
“走る!Necoライト”が「科学の入口」になる理由
“走る!Necoライト”は、手回し発電機のおもちゃです。
コンデンサーが組み込まれていて、発電した電気が貯められるようになっています。
そして、自分で発電した電気を、『動き』、『光』、『音』によって体験できます。
これが、子供の好奇心を刺激するようです。
1. シンプルな構造、ユニット交換ですぐに遊べる
“走る!Necoライト”は、
・動き:タイヤ
・光:豆電球ユニット、発光ダイオードユニット
・音:電子ブザーユニット
・貯める:コンデンサーユニット
が入っていて、このユニットを交換することですぐに遊べます。
いちいち配線をしなくても、ユニットを付け外しするだけ。
簡単なので子供の遊びたい気持ちを邪魔しません。
2. 電気を「自分で作る」体験ができる
ハンドルを回せば電気がコンデンサーに貯まっていきます。
そして、電気が貯まると『まんたんランプ』が点灯して知らせてくれます。
たくさんハンドルを回せば電気もたくさん貯まることが直感的にわかり、その電気を使うことで「自分で電気を起こした」体験ができます。
3. 自然と「なぜ?」が生まれる
家の中に光や音があるのは当たり前になっています。
でも、自分の手を動かして電気を起こすとで、『なぜ光るのか』、『なぜ音がするのか』といったことも気になるようでした。
そして、『家の中の家電製品を動かすためには、ハンドルを何回くらい回さないとダメなんだろう?』といった疑問も生まれたようでした。
自分で起こした電気を自分で使うからこそ、普段考えもしない「なぜ?」が生まれるようです。
子供にも説明できる簡単な発電のしくみ
専門知識がなくても、次のように説明すれば十分理解してくれます。
- 中には磁石とぐるぐるの銅線が入っている
- ハンドルを回すと、中の磁石ちかくを銅線が通過することで電気が生まれる
- できた電気がライトやモーターを動かす
『電磁誘導』とか『フレミングの右手(左手)の法則』とか、中学校の教科書で出てきたと思いますが、まさにその原理で発電しています。
ハンドルを回す運動を電気に変えているといってもよいかもしれません。
でも、難しい説明をしなくても、「ぐるぐる回すと電気ができる」と伝えれば子供は納得してくれます。
手回し発電機のおもちゃで身につく学び
比例関係の感覚
たくさんハンドルを回すほど長く走る、光る、音が鳴るといったことから、自分のした仕事の量と貯まった電気量の関係を体験的に理解できます。
エネルギーの仕組み
自分の力が電気になり、光や動きに変わることでエネルギー変換の基礎を学べます。
電気のありがたさに気づく
長時間回すのは疲れるため、普段の電気の便利さを自然と実感できます。
学びが広がる声かけの例
- 「なんでたくさん回すと明るいんだろう?」
- 「止めたらどうなるかな?」
- 「もし電気がなかったらどうなると思う?」
- 「停電の時にもライトとして使えるんじゃない?」
これらの問いかけによって、子どもが自ら考える習慣を育てられます。
実際に遊んでみた感想
電気は目には見えませんが、自分がハンドルを回すことで貯まることが分かり、とても楽しそうでした。
また、走らせたり光らせたりすることで、貯まっていた電気が使い切られることも不思議そうでした。
そして何より、走らせてり光らせたりするのがとても楽しそうにしていました。
まとめ
“走る!Necoライト”、シンプルながら子どもの探究心を育てる優れた『実験系のおもちゃ』です。
子供達が科学に興味を持つ入口として活用でき、親子で一緒に楽しめるのも魅力です。

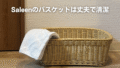

コメント